
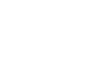


- 保育士資格は独学で合格できる?主婦におすすめの勉強方法を解説
-
2022.06.15 | 1,059 VIEWS
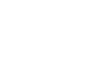


保育士資格は、試験を受けなくても得られる場合があります。
保育士養成学校に該当する大学・短大・専門学校などに2年以上在籍し、62単位以上修得または修得見込みである場合は、卒業後に保育士資格が与えられます。
この条件を満たしていない場合、保育士資格試験に挑戦しなくてはなりませんが、その場合も以下の条件を満たさないと受験資格を得られません。
【保育士資格試験の受験条件】
・4年制大学または短期大学を卒業している
・高校卒業後児童施設実務経験2年(2,800時間)以上
・義務教育終了後児童施設実務経験5年(7,200時間)以上
学歴により、満たさなくてはならない条件が違う点に注意してください。
特に、実務経験が必要な場合は、試験を受ける前に児童に関係した職業につかなくてはならないため、受験資格を得るのに年単位で時間がかかる点に気を付けましょう。
保育士資格は、受験条件によっては試験を受ける必要があります。
主婦の場合、独学で勉強する方が多いですが、保育士として働いている方の中には、子育て中や育休の間に試験勉強をして合格している方もいます。
実務経験が必要な場合、試験に向けて就職活動も必要になりますが、独学で保育士資格を取得し、活躍している方はたくさんいます。
保育士資格は、主婦でも独学で取得可能な資格だといえるでしょう。
保育士資格は、筆記試験と実技試験のふたつの試験をクリアしなくてはなりません。
試験は筆記試験のあと実技試験に挑戦する形をとりますが、実技試験を受けるには筆記試験で全科目合格する必要があります。
両方の試験内容をよく理解し、入念に対策をしておきましょう。
まずは筆記試験の出題科目と問題数を確認しましょう。
以下の図は、出題科目と問題数を一覧にまとめたものです。
| 出題科目 | 問題数 |
|---|---|
| 保育原理 | 20問 |
| 教育原理および社会的養護 | 20問 (教育原理10問・社会的養護10問) |
| 子どもの家庭福祉 | 20問 |
| 社会福祉 | 20問 |
| 保育の心理学 | 20問 |
| 子どもの保健 | 20問 |
| 子どもの食と栄養 | 20問 |
| 保育実習理論 | 20問 |
実技試験に進むには、この科目すべてに合格しなくてはなりません。
独学で勉強する際は、内容をしっかり理解しておきましょう。
筆記試験に合格後、実技試験に挑戦できます。
実技試験は音楽・造形・言語の3つの分野のうち、ふたつを選択する必要があります。
どの分野を選択するかも、試験合格のカギです。
分野ごとの詳しい試験内容を確認して、どの分野なら有利に試験へ挑めるかを考えながら選びましょう。
分野の詳しい試験内容は、以下の図のとおりです。
| 分野 | 試験内容 |
|---|---|
| 音楽 | ・幼児に歌って聞かせることを想定し、課題曲2曲を弾き歌いする ・課題曲は試験年により変わるが、童謡が多い ・使用できる楽器はピアノ・アコースティックギター・独奏用のアコーディオン ・保育士として必要な歌・伴奏の技術・リズムなどを総合的かつ豊かな表現ができること |
| 造形 | ・課題として提示された保育の一場面をA4の回答用紙内に19cm×19cm以内の絵画で表現する ・課題の問題文と条件は当日提示 ・使用できる道具はHB〜2Bの鉛筆またはシャープペンシル・12〜24食程度の色鉛筆・消しゴム・アラームが鳴らない腕時計 ・道具はイラスト入りのものはすべて持ち込み不可 ・保育の状況をイメージした造形表現 |
| 言語 | ・3歳児クラスの子どもに「3分間のお話」をする状況を想定し、課題からひとつを選択・子どもが集中して聴けるようなお話を行う ・課題はおむすびころりん(日本の民話)・ももたろう(日本の民話)・三匹のこぶた(イギリスの昔話)・三びきのやぎのがらがらどん(ノルウェーの昔話) ・絵本や道具(台本・人形)などは一切使用禁止 ・保育士として必要な基本的な声の出し方・表現上の技術・幼児に対する話し方ができる |
どれも保育士として幼児に対する表現力を求められる試験です。
音楽の課題を見るとわかりますが、楽器演奏の技術力はそれほど求められていません。
大切なのは、子どもの保育を遂行するうえで、必要な力があることの証明です。
とはいえ、ある程度の試験対策は必要になります。
筆記試験ばかりに集中せず、実技試験の対策も入念に行っておきましょう。
保育士資格試験は、実施される日程がある程度決まっています。
独学で勉強する際は、試験日程を軸にしてスケジュールを立てましょう。
| 前期 | 4月 |
|---|---|
| 後期 | 10月 |
| 前期 | 6月 |
|---|---|
| 後期 | 12月 |
保育士資格試験は、毎年2回行われ、前期と後期ではスケジュールが違います。
独学の計画を立てる際は、日程を間違えないようにしましょう。
保育士資格試験は、まず筆記試験に挑戦します。
筆記試験は各教科100点満点中60点以上を取得すると合格になります。
この中のうち教育的原理および社会的養護は、それぞれ50点満点中30点を取らなくてはなりません。
これは、ふたつの分野が合わさって科目を作っているためです。
実技試験は1分野50点満点中30点・合計60点以上で合格になります。
筆記試験とは違い、具体的な採点基準や加点・減点の理由は公開されていません。
これらの内容は試験後に質問しても答えられないため、試験対策をする際はテキストなどから注意点を読み取り、独自に対策していく必要があります。
保育士資格試験は、筆記試験と実技試験で対策方法が大きく違う点に注意しましょう。
次に、保育士の合格率ですが、その年により変化はあるものの20%台が多いです。
これは筆記試験の科目の多さや、受験者の多さが関係しています。
主婦業をこなしながら独学で受験する場合は、ほかの受験者に負けないように入念な試験対策を行わなくてはなりません。
保育士資格の筆記試験は、全科目に合格できない場合でも、一度合格した科目は3年間有効とされます。
つまり、3年間の間に筆記試験を全科目合格し、実技試験をクリアできれば、保育士になることが可能です。
保育士資格試験は合格率が非常に低い資格のため、しっかりとした試験対策が必要です。
万が一落ちても3年間はチャンスがあります。
不合格になっても、あきらめずチャレンジしましょう。
主婦が保育士資格試験に挑戦する場合、3つの方法が選択できます。
【主婦が保育士資格試験に挑戦する際の勉強方法】
・独学
・通信講座
・養成所に通う
主婦業をこなしながら養成所に通うのは、少々難しいと感じる方が多いでしょう。
実際主婦をしながら保育士資格試験に合格した方の多くが、独学か通信講座で勉強しています。
この記事では、独学と通信講座を利用して勉強する場合のやり方・メリット・デメリット・費用などを解説します。
独学で保育士資格試験に挑戦する場合、書店などに販売されている参考書や問題集をもとに勉強します。
テキストの問題をひととおり解きながら、内容を理解するのがポイントです。
筆記試験の場合は、内容理解だけでなく過去問をひたすら解いて、問題になれることが大切です。
問題を解きながら内容の理解を進めていくと、効率的に勉強できます。
実技試験の勉強方法は、挑戦する分野により違います。
試験内容をよく理解したうえで、トレーニングを行いましょう。
試験では制限時間が決められているため、時間内で作業を終了できるように訓練しましょう。
独学の場合にかかる費用ですが、テキストや問題集を複数購入すると、大体合計で2,000〜4,000円前後になります。
実技試験に必要な楽器や道具をそろえる場合は、そのための費用も別途かかることも覚えておきましょう。
独学の場合、自分のペースで勉強できるうえに、費用もあまりかかりません。
通信講座も自分のペースで勉強できますが、ある程度はカリキュラムに従う必要があります。
また、費用が基本的にテキストや問題集を購入する費用だけで済むのも、独学の魅力的なポイントです。
自分のペースで試験対策を行いたい方や、できるだけ試験にお金をかけたくない方は、独学で勉強した方がスムーズに試験対策ができます。
メリットがたくさんある独学ですが、デメリットもあります。
独学の場合、試験対策だけでなく、試験に向けてのスケジューリングや試験傾向の調査なども自分で行わなくてはなりません。
また、基本的にひとりで黙々と勉強するため、孤独を感じやすいでしょう。
学習計画の立案・管理や、試験内容や傾向調査が苦手な方、ひとりで黙々と作業をするのが苦手な方は、独学と相性が悪いといえます。
つぎに、通信講座についてです。
通信講座は、保育士資格試験の試験対策では一般的な方法です。
取り扱う通信講座会社も増えており、講座の中には合格率が6割以上と高い実績を持つところもあります。
勉強は通信講座のカリキュラムに従い、筆記や実技の対策を行います。
WEBや郵送の添削によりに、講師と連絡を取り合いながら勉強するのが基本の流れです。
費用は通信講座会社や、通信講座のコースにより変わりますが、概ね4〜6万円台が多いです。
通信講座の場合、カリキュラムが試験日程にあわせて設定されていることが多いです。
カリキュラムにあわせて勉強すればいいため、自分でスケジューリングする必要はありません。
通信講座の教材として試験対策に必要なものがある程度用意できるため、試験に使う道具を用意する手間が省けるのもメリットのひとつです。
また、インターネットや郵送を通して講師に実力をチェックしてもらえます。
苦手な科目や、勉強が足りない部分など、自分では気が付きにくい点も確認できるため、よりしっかりと試験対策ができるでしょう。
一方でメリットとしては、費用が独学よりもかかることがあげられます。
通信講座の場合、講座を受講するための費用が必要です。
費用を用意できない場合は、利用を見送らなくてはなりません。
また、カリキュラムがある程度決まっているため、完全に自分のペースで進めることができません。
自分のペースで勉強したい場合は、通信講座よりも独学の方が適しています。
試験対策にかけるお金を少しでも抑えたい方や、自分のペースが乱れると勉強しにくいと感じる方は、独学での勉強をお勧めします。
保育園や保育所は、保育士の資格を最大限に活かせる場所です。
求人サイトなどを見るとよくわかりますが、保育士資格を活かせる職場の中でも、特によく募集がかかる職場でもあります。
保育士資格を持っている場合は、正社員での就職や転職が多いです。
一方、無資格の場合はパートやアルバイトでの募集がほとんどになります。
勤務形態に関わらず、無資格では保育士資格を持っている場合よりも給与が安いなど、待遇面で差が生まれている傾向にあります。
これは、法律が関係しています。
保育園や保育所は「児童福祉施設の設備および運営に関する基準」の法令により、預かっている子供の年齢に応じて、保育士資格を取得した職員を配置しなくてはなりません。
職員の最低配置数を守らない場合は、法律違反となります。
法を守り、安全に保育園や保育所を運営するには、保育士の配置が重要です。
また、自治体により保育士の数に応じて助成金が出る場合があります。
条件を満たせば追加支給を受けられるため、保育園や保育所は積極的に保育士資格を持つ人材を雇用します。
保育園や保育所は、保育士が活躍できる職場であり、実務経験を積むのに最適な職場です。
しかし、法律や助成金の関係から、雇用形態や待遇に差が生まれる可能性があることを覚えておきましょう。
保育園や保育所のような専門施設でなくても、子どもを預かる必要のある店舗や施設はたくさんあります。
このような施設で、保育士が募集されていることもあります。
【保育士を募集している施設の一例】
・美容院
・歯科医院
・企業や組織の職員用施設内保育所
・大病院の院内保育所
・大病院の小児科にある病児保育室や院内保育
・商業施設の託児所
これらの施設の職場も、保育士資格を活かす就職や転職のチャンスです。
子どもを預かる仕事は施設内の保育所だけでなく、ベビーシッターなどの預かり先へ出勤する方法もあります。
働き方にこだわらず、保育士資格が必要であることに注目して仕事を選べば、さまざまな働き方が可能になります。
子どもを預かる仕事は、義務教育を迎えていない子どもを対象としたものだけではありません。
放課後デイサービスや学童などの小学生を預かる施設も、保育士の就職先です。
現在、共働き世帯の増加により、放課後デイサービスや学童の需要は高まりつつあります。
そこで働く保育士も同じです。
放課後デイサービスや学童であれば、相手をするのは主に小学生のため、幼児や乳児が苦手な方でも働けます。
子どもは好きだけど会話が難しい子どもや、トイレなどの世話が必要な子どもに接するのは抵抗を感じる方は、放課後デイサービスや学童を中心に就職・転職活動をするといいでしょう。
このほか、少々変わった仕事ですが、第三者評価調査員の仕事も保育士資格を活かせます。
保育園などには、活動や取り組みを評価する「第三者評価制度」と呼ばれる制度があります。
調査員の資格は自治体により異なりますが、条件を満たせば保育士の資格を活かしながら仕事ができます。
保育士資格を活かせる仕事のひとつとして、覚えておきましょう。
初めて保育士資格に挑戦する場合、学習目安は大体150時間前後になります。
これは筆記試験の勉強時間目安が関係しています。
【筆記試験の勉強時間目安】
・内容を覚える時間目安:40時間
・過去問や問題集を解くのにかけるべき時間目安:110時間
筆記試験に合格するには、これらの目安を目標に勉強しなくてはなりません。
スケジューリングは試験日程にあわせて計画的に行いましょう。
保育士資格試験は、人により数か月〜1年で合格しようとする方と、2年近くかけて合格しようとする方の2パターンがあります。
勉強にかける期間により、スケジュール内容もかなり変わるため、独学の場合は注意が必要です。
通信講座も講座を提供している企業やコースによりカリキュラムが違うため、申し込みの際は必ず確認してください。
独学でも通信講座でも、主婦である以上家事や育児をこなしながら挑戦することになるでしょう。
兼業主婦の場合は、これに加えて仕事もこなさなくてはなりません。
主婦はどうしても、まとまった時間の確保が難しいといえます。
まとまった時間を確保できない状態で資格試験に挑戦する場合、移動中や家事の合間などのスキマ時間を利用して勉強する形になります。
スキマ時間をどれだけ有効に勉強できるかが、主婦の保育士資格試験合格のカギです。
スキマ時間の勉強方法は、以下のようなアイデアがあります。
【スキマ時間を利用した勉強アイデア】
・スマホなどに音声データで試験内容を取り込み移動時間などに聞く
・お風呂などの時間にテキストを持ち込んで勉強する
主婦業をこなしながら勉強をする場合は、スキマ時間をどうすれば勉強時間に変えられるかを考えておきましょう。
保育士資格に挑戦する場合は、家族にもその旨を伝えておきましょう。
ときには家族の助けを受けることも、主婦が保育士資格に合格するには必要なことです。
家事や育児をほかの家族に代わってもらえば、資格試験に必要なまとまった時間を確保できます。
実技試験の中には子どもが参加できるものもあるため、協力してもらうといいでしょう。
工夫次第でいろいろな協力方法があります。
まとまった時間を少しでも確保できれば、より入念な試験対策が可能です。
保育士資格に挑戦する際は、家族にもそのことを伝え、ときには手伝ってもらいましょう。